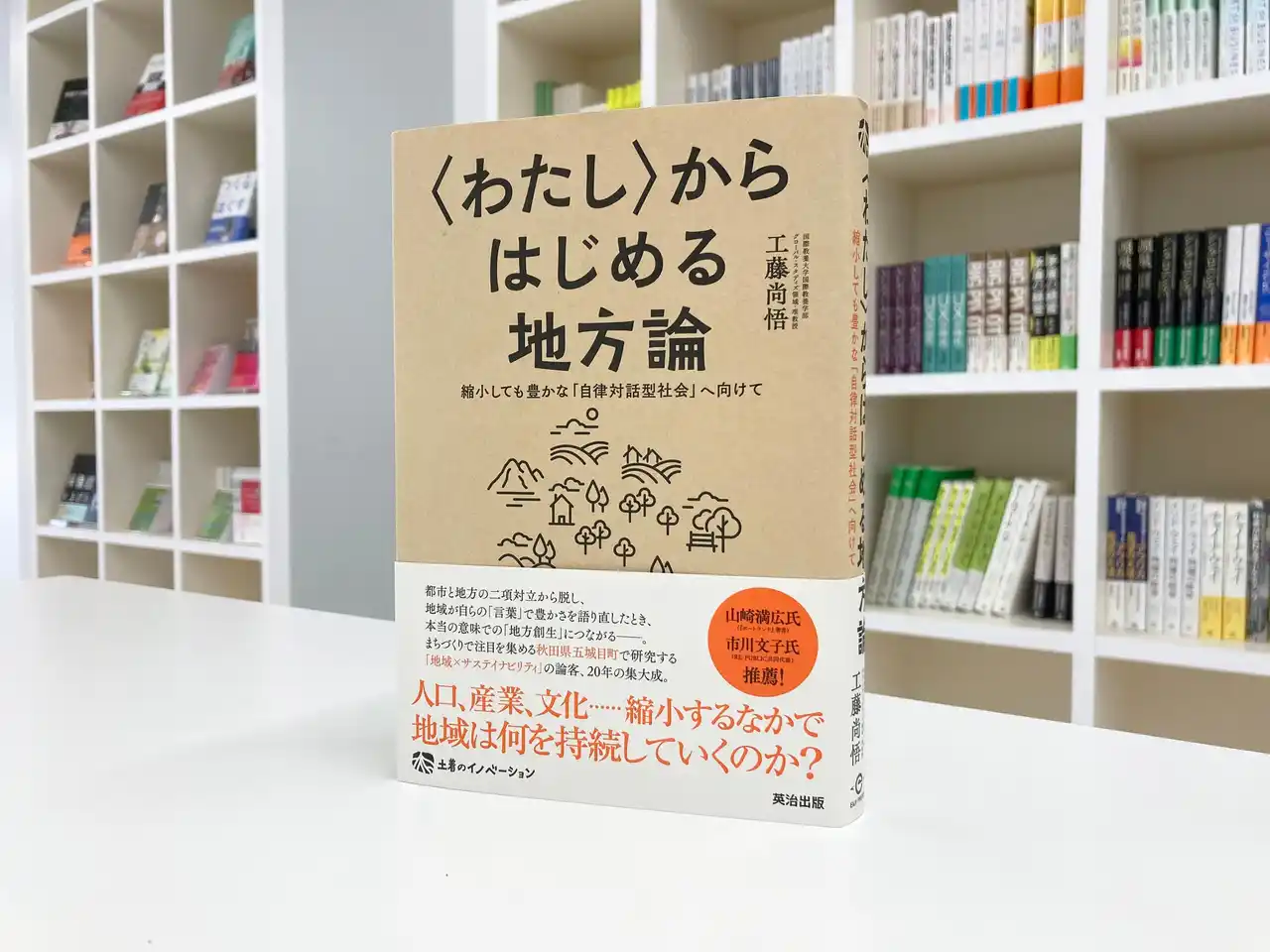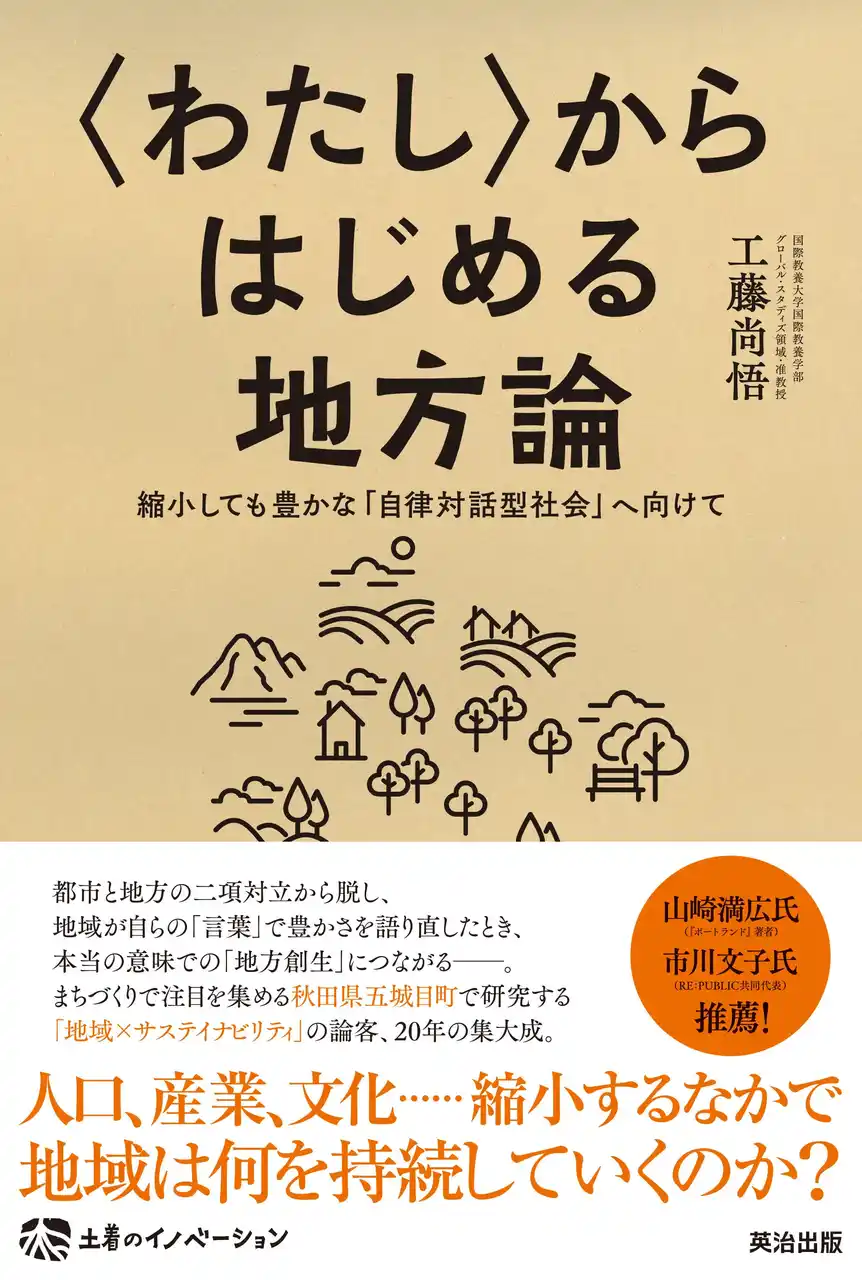|
縮小していくなかで、地域は何を持続していくのか。希望の道筋を照らす『〈わたし〉からはじめる地方論』、英治出版「土着のイノベーション」第二弾として8月7日(木)発売!
|
|
|
|
|
|
|
英治出版株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:高野達成)は、2025年8月7日(木)に、秋田県五城目町の事例をもとに、いま最も問われるべき地域の持続可能性を記した『〈わたし〉からはじめる地方論』を刊行いたします。本書は、地域に長く根を張り、世代を超えて持続的な変化をもたらす実践や取り組みを記録し、次世代に伝えていくためのレーベル「土着のイノベーション」の第二弾です。 |
|
|
|
|
|
秋田県五城目町──500年続く朝市と、山・湖の織りなす風景、そして豊かな文化資本をもつこのまちは、人口減少が進むなかで注目を集める地域のひとつです。今、この地では、地域に暮らす人と外から訪れる人が交わりながら、自律的に、そして主体的に動き出す「うねり」が生まれています。 |
この地域で起きている変化を捉え、「縮小しても豊かさは実現できる」という未来像を描くのが、本書『〈わたし〉からはじめる地方論』(著:工藤尚悟)です。英治出版のコンテンツレーベル「土着のイノベーション」第二弾として刊行される本書は、いま最も問われるべき地域の持続可能性を、〈わたし〉=地域に暮らす一人ひとりの視点から再構築します。
|
|
|
|
「地方創生」の次に本当に必要な問いとは? |
|
|
|
政府による「地方創生」が打ち出されてから10年、2025年には新たに「地方創生2.0」の基本構想が発表されました。こうしたなか、「地域を盛り上げなければならない」という空気が当たり前となりつつあります。 |
|
しかし本書の著者である工藤尚悟氏(国際教養大学准教授)は、この風潮に対し警鐘を鳴らします。 |
|
「“地域活性化”、“限界集落”、“消滅可能性都市”といった言葉はすべて中央から与えられたものであり、都市と地方という二項対立に基づいている」と。 |
|
その結果、地域に生きる人々が自らの言葉を失い、中央の論理や外部のコンサルタントに頼らざるを得ない構造が生まれているのです。 |
|
|
|
|
|
地域の未来をつくるのは、そこで暮らす「わたし」の言葉 |
|
|
|
では、本当に問うべき何か。工藤氏は、「人口が減るなかで、何を持続していくのか」という視点だと言います。 |
・「地方創生」と言いながら、そこに暮らす人たちの価値観が問われていない。
・「消滅可能性都市」と言いながら、何が消えると困るのかは語られていない。 |
|
本書では、地域を単に都市と対置させるのではなく、「訪れる人」と「暮らす人」が交わる〈あいだ〉にある場として捉え直すことで、地域側からの語りが生まれる可能性を示します。 |
|
|
|
|
|
縮小と豊かさを両立する、五城目町の5つの特徴 |
|
|
|
五城目町では、「縮小しても豊かに暮らす」ための数々の実践が行われています。本書ではその具体例として、以下のような取り組みが紹介されています。 |
|
まちとつながる場所がある(多様な働き方を支える「ババメベース」) 「小さな企て」が起きている(住民の背中を押す「いちカフェ」や「まちのヒーローアカデミア」) 異質なものが流れ込む(対話と観察を支える「ものかたり」や「シェアビレッジ」) 自ら学ぶまち(学校づくりへの住民参加「スクールトーク」や「みんなの学校」) 誰かの「やってみたい」が具現化しやすい場がある(挑戦の場「朝市plus+」、自己表現の場「貸し棚おうみや」) |
|
これらの動きは、人口減少社会においても、地域が主体的に変化を生み出し、持続可能な未来を切り拓いていく力を持っていることを示しています。 |
|
|
|
|
|
|
|
■著者略歴 |
|
|
|
工藤尚悟(くどうしょうご) |
|
国際教養大学国際教養学部グローバル・スタディズ領域・准教授。サステイナビリティ学博士。 |
|
持続可能な社会の実現に学際的に取り組むサステイナビリティ学分野において、持続可能な地域コミュニティに関する研究・教育に取り組む。秋田と南アフリカのフィールドを往来しながら、異なる風土にある主体が出会うことで生まれる”通域的な学び (Translocal Learning)" という方法論の構築に取り組んでいる。 |
|
|
|
|
|
■書誌情報 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
■「土着のイノベーション」とは? |
|
|
|
|
|
|
変化は、遠くの大計画からではなく、足もとの暮らしのなかから生まれます。
「土着のイノベーション」とは、地域に根ざし、世代を超えて持続する変化の芽に光を当てるムーブメントです。英治出版では、この視点を軸に、世界各地の地域変容の実践を紹介するシリーズを展開しています。 |
|
|
|
本レーベルが大切にしたいこと |
|
1 変容の当事者性 |
|
生活・暮らしは、わたしたちの手で変えられるという実感を届ける |
|
2 「私」と社会のつながり |
|
自分に根ざす取り組みが、社会に根を張る変容を起こす |
|
3 Place-Basedな視点 |
|
土地・歴史に根ざしたまなざしをわすれない |
|
4 ポジティブなレガシー |
|
世代を超えてつないでいきたい「変化のプロセス」を残す |
|
5 インパクトの可視化 |
|
唯一無二の取り組みに眠る「普遍的な価値」をすくい上げる |
|
|
|
|
■会社概要
|
|
社名:英治出版株式会社 |
|
本社所在地:東京都渋谷区恵比寿南1-9-12 ピトレスクビル4F |
|
代表取締役:高野達成 |
|
設立:1999年6月 |
|
HP:www.eijipress.co.jp
|
|
英治出版株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:高野達成)は、2025年8月7日(木)に、秋田県五城目町の事例をもとに、いま最も問われるべき地域の持続可能性を記した『〈わたし〉からはじめる地方論』を刊行いたします。本書は、地域に長く根を張り、世代を超えて持続的な変化をもたらす実践や取り組みを記録し、次世代に伝えていくためのレーベル「土着のイノベーション」の第二弾です。