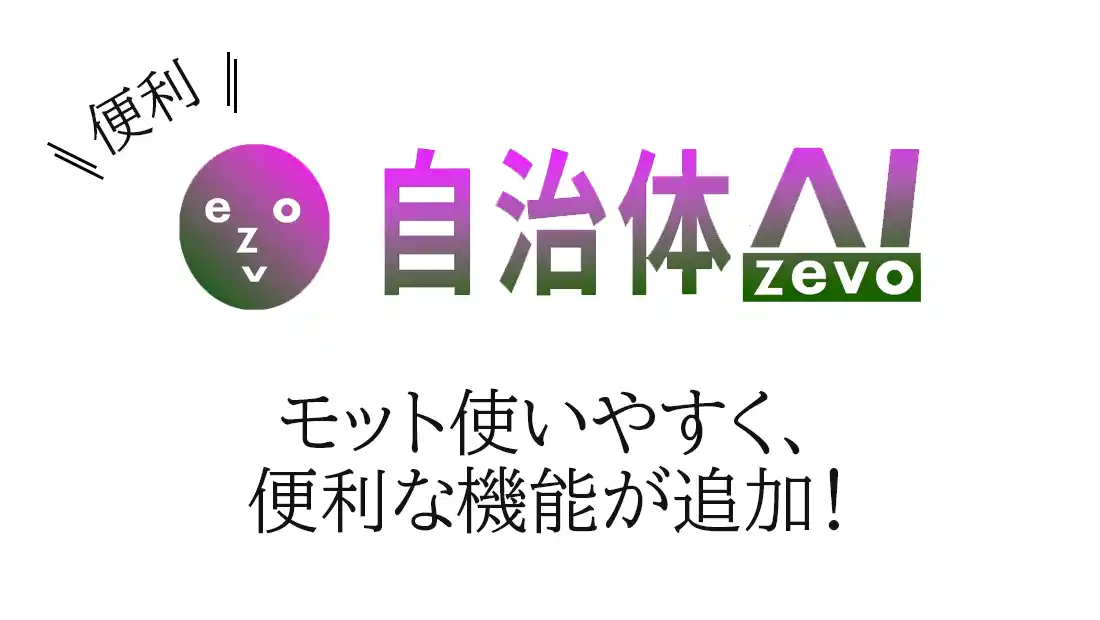|
シフトプラス株式会社(代表取締役:中尾 裕也、本店:宮崎県都城市宮丸町3070番地1/本社:大阪府大阪市西区江戸堀2丁目1番1号 江戸堀センタービル8階/以下シフトプラス)は都城市と共同開発を行った、ChatGPT/Claude/Geminiなどの生成AIを自治体のLGWAN環境で活用できるシステム「自治体AI zevo(ゼヴォ)」において、細かい機能追加を行なったことをお知らせいたします。 |
|
|
|
■自治体AI zevo アップデートのお知らせ~さらに便利に~ |
|
|
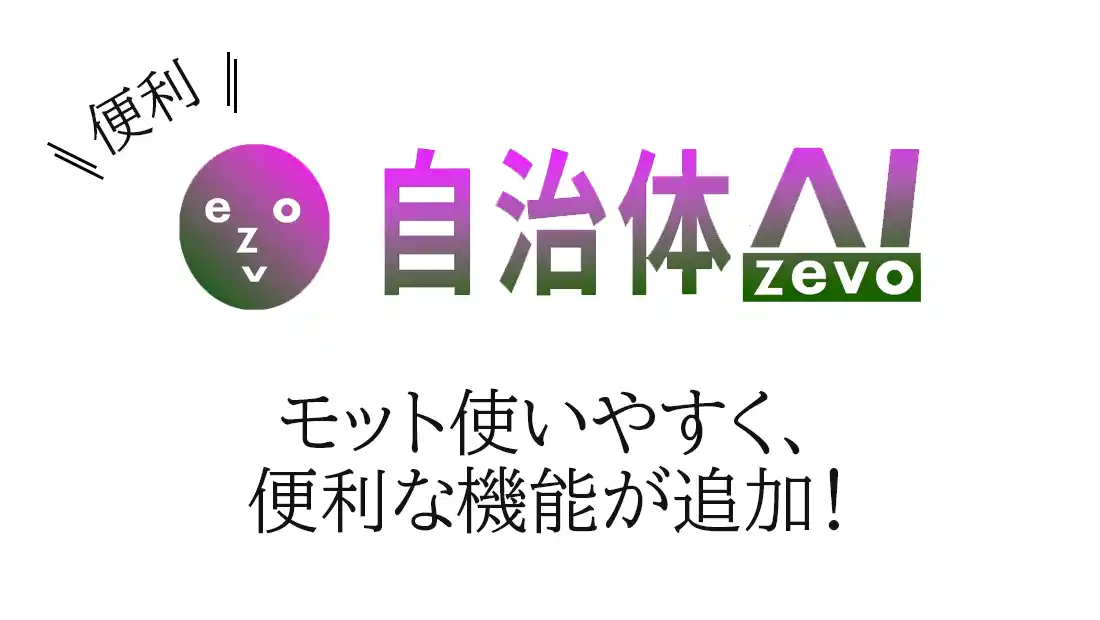
|
|
|
|
もっと便利に、使いやすくをモットーに! |
|
|
|
|
1. ユーザーのプロンプトを改善できる機能を追加 |
|
|
|
多くのユーザーが抱える悩みとして、次のような課題がありました。 |
|
|
|
• |
|
|
• |
|
効果的な回答を得るためのプロンプトがなかなか書けない |
|
|
|
|
|
自治体AI zevoではこれらの課題を解決するため、入力したプロンプトを生成AIに改善してもらえる機能を追加しました。この機能を活用することで、生成AIがプロンプトの作成をサポートするので、初心者のユーザーの方でも生成AIにより効果的な質問ができるようになり、より効果的に生成AIの活用が可能となります。 |
|
|
|
|
|
2. プロンプト例(テンプレート機能)に実行時オプションを設定が可能に |
|
|
|
これまでプロンプト例を実行する度にユーザーがそれぞれAIモデルや独自AIの選択、会話履歴やウェブ検索設定のON/OFFを設定する必要がありましたが、この度プロンプト例に実行時にAIモデル、会話履歴の設定、RAGの設定、WEB検索機能の設定のオプションを設定し保存できるようにいたしました。今回のアップデートで柔軟なプロンプト例の作成が可能となり、より効率的な業務運用をサポートできると考えております。 |
|
|
|
|
|
3. RAG(機能名:独自AI)にウェブページの内容を追加可能に |
|
|
|
RAGの参照元として、指定されたURLから内容を抽出し、その内容を独自AIへ登録できるようになりました。これにより、最新の情報をよりシームレスに独自AIへ反映できます。 |
|
|
|
|
|
4. 音声ファイルアップロード機能の対応ファイルが増加 |
|
|
|
プロンプトの入力時にアップロード可能な音声ファイルの形式に、新たにm4a形式のファイルにも対応いたしました。これにより音声ファイルの対応の幅が広がり使い勝手が向上しました。 |
|
音声認識が可能なAIモデルGemini 1.5 Flash / Pro・Gemini 2.0 Flash / Flash Lite・Gemini 2.5 Flash / Pro / Flash Liteとなります。 |
|
|
|
|
|
自治体AI zevoでは今後も多くのユーザーの方にとって、便利で使いやすい生成AIプラットフォームとなるように機能追加を行なってまいります。引き続き自治体AI zevoをよろしくお願いいたします。 |
|
|
|
|
|
■自治体AI zevoは繋がる、広がる、さらに便利に |
|
|
|
ビジネスチャットツール LGTalkを提供 |
|
|
|
「自治体AI zevo」をご契約いただいた場合、付帯サービスとしてビジネスチャットツールLGTalk職員数分のアカウントを提供いたします。LGTalkはファイル無害化などセキュリティを重視したチャットツールです。チャット上から直接生成AI(自治体AI zevo)を利用することが可能です。 |
|
10アカウントまで利用可能なトライアルも提供しております。 |
|
|
|
eRexと連携が可能に |
|
|
|
LGWAN専用音声認識AI文字起こしツール「eRex」と連携可能です。eRexから自治体AI zevoと連携して文字起こしの結果をシームレスに要約できます。「eRex」についても1ヶ月間の無償トライアルを実施しております。 |
|
ご興味ございましたらお気軽にお問い合わせください。 |
|
今後も継続して、より便利に、より活用シーンが広がるよう機能追加を行なってまいります。 |
|
今後とも、シフトプラスならびに「自治体AI zevo」をよろしくお願いいたします。 |
|
|
|
製品LP |
|
|
|
自治体AI zevo:https://www.lgsta.jp/zevo/
|
|
LGTalk:https://www.lgsta.jp/lgtalk/
|
|
eRex:https://www.lgsta.jp/erex/
|
|
|
|
シフトプラス株式会社について |
|
|
|
シフトプラス株式会社は、2006年12月に大阪市西区に設立され、Webシステムの提案・設計・構築・保守、および地方自治体向けシステム開発コンサルティング、業務委託サービスを行っております。本社を大阪市西区に置くほか、日本国内23カ所に営業所を置いています。「ふるさと納税」管理システム LedgHOME<レジホーム>の自社開発とそれに関連する業務を行っており、北海道から九州まで500以上の自治体が導入(2024年3月末時点)しており、日本全国の寄附額の約50%を管理しています。 |
|